私は断ることが苦手。
仕事でもプライベートでも、頼まれたことを断ることができない。
なんだか申し訳ないし、頼まれごとをこなせない自分に価値がないと思ってしまうから。
断るのが怖い。
「あれやっといて」「これよろしく」
はいはい言っているうちに、そこそこ優秀な便利屋ポジションになっていた。
便利屋として生活できるくらいには需要があった。
世間では「すごいじゃん!」と言われるかもしれない。
それを聞いて、心の奥で苦虫を嚙み潰す。
極端に実力があるわけではない。頭はよくない。
ただの器用貧乏。
歯車にすらなれず、その間に垂らされる油のような日々。
心も黒ずんでいった。
眠れない夜は、街灯のまばらな田舎道を歩いた。
剥がれたアスファルトの感触がごろごろと足の裏に伝わり、立ち止まっては暗闇に心を溶かした。
そうすると気持ちが楽になって眠ることができた。
ある時、体調を崩した。
我慢の貯蔵量が限界を迎えたようだ。
自分の人生の価値について考えた。
一生この日々に体中を縛り付けられ、コントロールできない他人の感情の波にのまれ、泡となって消えていくのか。
もう死んでいると思った。
その人生は死んでいる。
自分を押し込めて、自分のいなくなった世界で奔走する、自分。
それはいったい誰なんだ。
ふと、子供の頃を思い出した。
外から見るといい家庭、中から見ると思想の鎖で締め上げる家庭。
頑張る。「まだまだ甘い」
嫌い。「我慢しなさい」
嬉しい。「浮かれるな」
悲しい。「お前が悪い」
意見。「存在しない」
家の中で、自分は自分ではなくなった。
大人になって、どうやら世の中はもう少し自由なのだと知った。
お菓子は食べていいらしい。
肉も食べていいらしい。
味をつけてもいいらしい。
我慢はもっと少なくていいらしい。
少しずつ世界は広がっていった。
でも自分を優先するということが、どうしても苦手だった。
人の頼みを聞いて、人に感謝されて、忙しくなって疲弊して、やっと自分が居ていいと思えた。
祖母が亡くなった。
なかなか会えなかったけど、優しくて大好きな祖母だった。
たまに会いに行くと、自分の好きな食べ物を用意してくれていた。
数少ない、人格を尊重してくれる人だった。
祖母の葬式は仕事を優先して、通夜だけ行った。
たしか休むこともできたはず。
上司も「休め」と言ったはず。
なぜだかそれは断った。
多忙な自分に酔っていたのだろうか。
それが真面目だと思っていたのだろうか。
どうやらこれまでの自分は、望む状況を望んではいけなかったらしい。
不幸だけど頑張っている自分でいなければならなかったらしい。
そんな自分でいなければ、価値が感じられなかったらしい。
クソ馬鹿。
本当に大切なものを考えた。
本当に大切な人のことも考えた。
たくさん傷つけられたけど、違う人をたくさん傷つけてきた。
何を守るために、何を守っていたのだろう。
目がかすんで、何も見えていなかった。
何も大切にはしていなかった。
暗闇の中を、泣きながら走っていた。
その両の手の平から、大切なものをボロボロと零しながら。
足が止まりそうになると目の前に、よく酔える不幸が置いてある。
それを目指してまた走る。
それを灯りに、それを頼りに。
手の平が軽くなるほど、不幸は拾いやすかった。
不幸を拾うほど、手の平は軽くなっていった。
見えない幸せを目指して、暗闇へ向かって走っていた。
不幸が照らしてくれたから。
でも、そろそろ立ち止まっていいかもしれない。
立ち止まって、拾い物をやめて、少し見上げてみてもいいのかもしれない。
ほとんど何にも無くなって、やっと立ち止まることができた。
苦虫を咥えながら、やっと立ち止まることができた。
やっと立ち止まることができた。
空は薄っすら青くて太陽は少し赤い。
ここから。
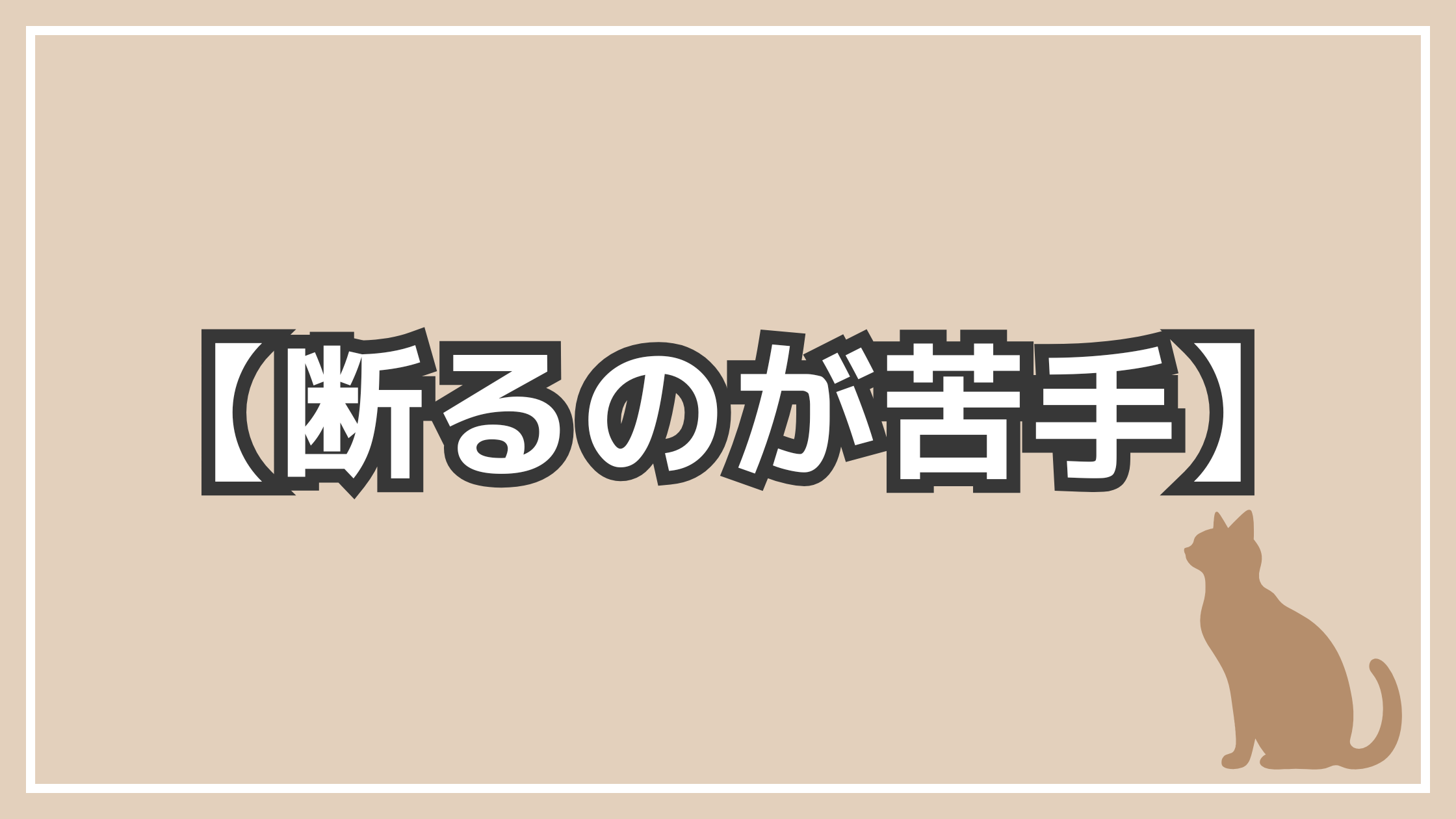


コメント